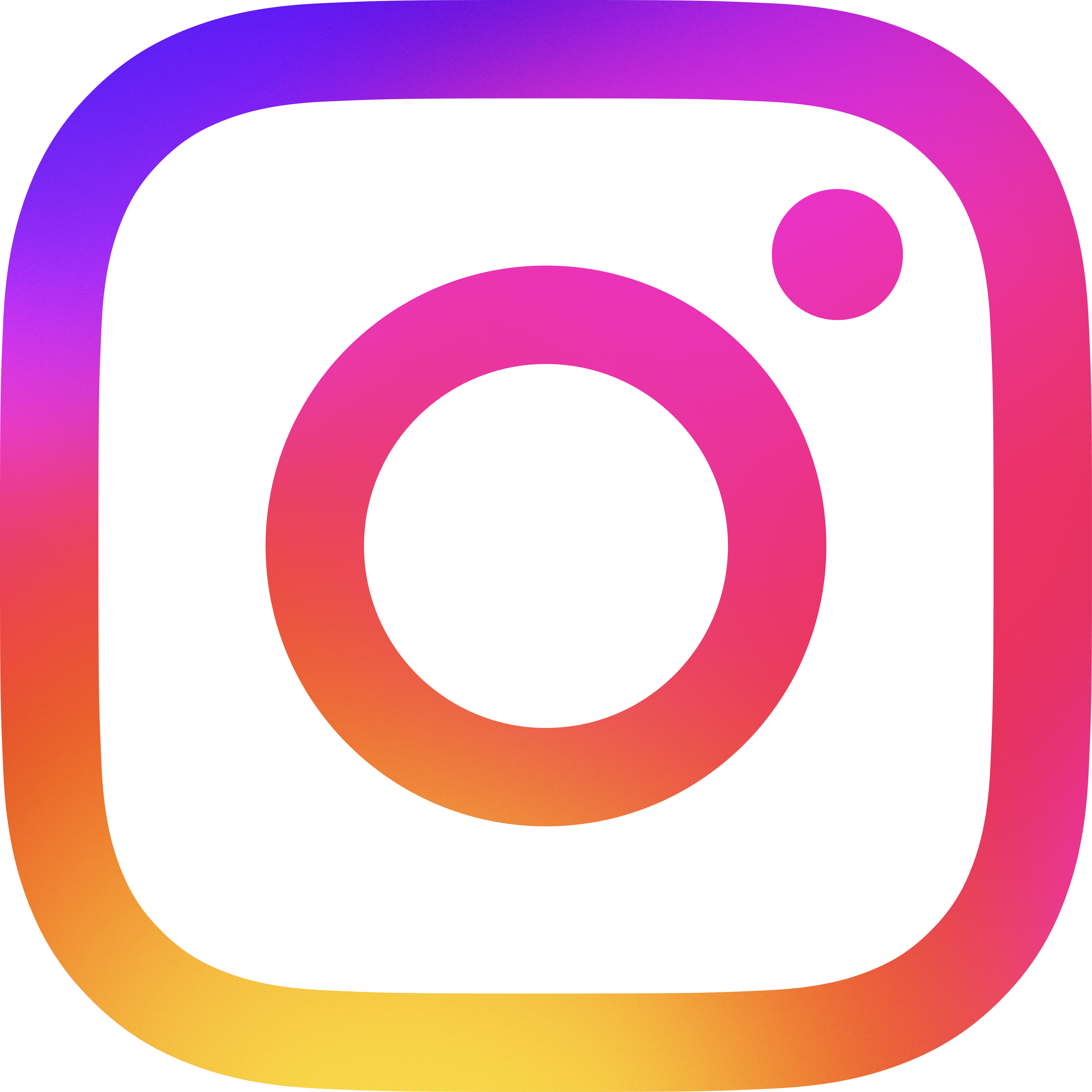門部王の万葉集

意宇平野にある出雲国府の情景
出雲国府は、奈良時代のはじめ690年頃に意宇平野に設けられた。国府周辺には、古墳時代に山代二子塚古墳などの前方後方墳、大型方墳、多数の横穴墓群が築かれ、墳墓の被葬者となる力を持った人々が連綿と暮らし続けた六所神社周辺がある。
門部王(かどべのおおきみ)は、『出雲国風土記』が編纂される頃に出雲国司として赴任していたとされ、万葉集に歌を書いている。
意宇平野は、東西5km、南北3kmの平野で、およそ3万年前の河川堆積物を最下底にしている。縄文海進以降の海面低下にともなって、意宇川(いうがわ)が三角州を形成し、縄文時代の後期には湿地を残しながら陸化したと考えられている。
写真は阿太加夜神社にある門部王の絵
- 歴史・文化サイト

阿太加夜神社境内の歌碑

風土記の丘