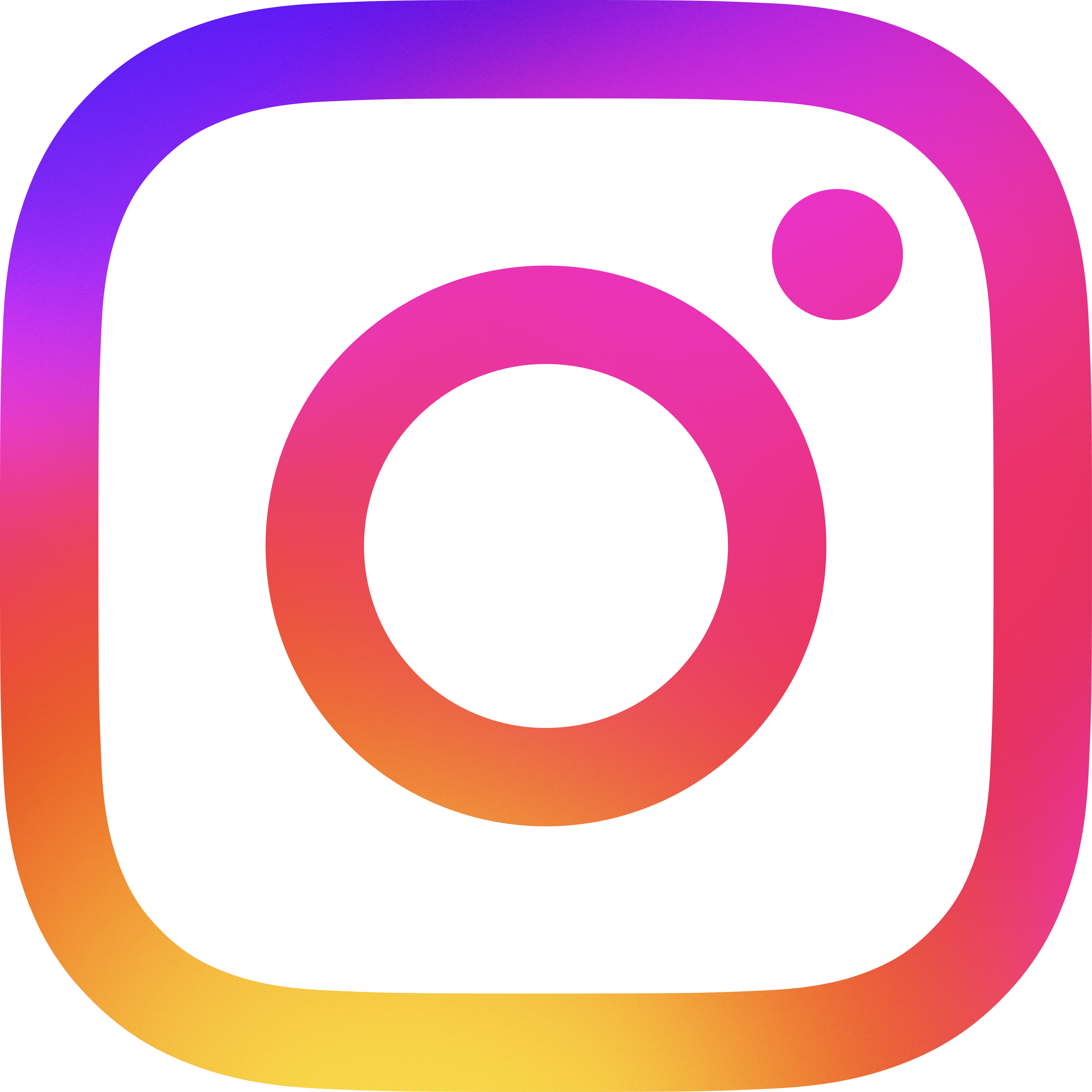手結のスランプ褶曲

大蛇のように曲がりくねった地層
手結では、約1600万年前の灰白色の凝灰質礫岩・粗粒砂岩層の中に黒色頁岩層が曲がりくねってひと塊となった地層が見られる。曲がりくねった地層の形状はスランプ褶曲とよばれる。スランプという言葉は、不調で何をしても上手くいかないときによく使われるが、「突然に滑り落ちる」とか「ドスンと落ち込む」のような意味もある。この言葉から察することができるように、この地層はまだ十分に固まっていない粘土の地層が海底の斜面を急激に滑り落ちる過程で曲がりくねってできたものである。
【カテゴリー】
〇島根半島エリア(ジオヘリテイジ)
・探訪サイト(ジオヘリテイジについて探訪し、学び、教育・研究活動をすることのできる地点)
- 地質サイト

DSC02815
ACCESS
未来の子供たちが現在の私たちと同じように、今の美しい自然環境を利用できるようにするためにも、著しい環境の改変につながるような動植物や岩石等の採取等の自然環境の破壊は厳に慎んでください。