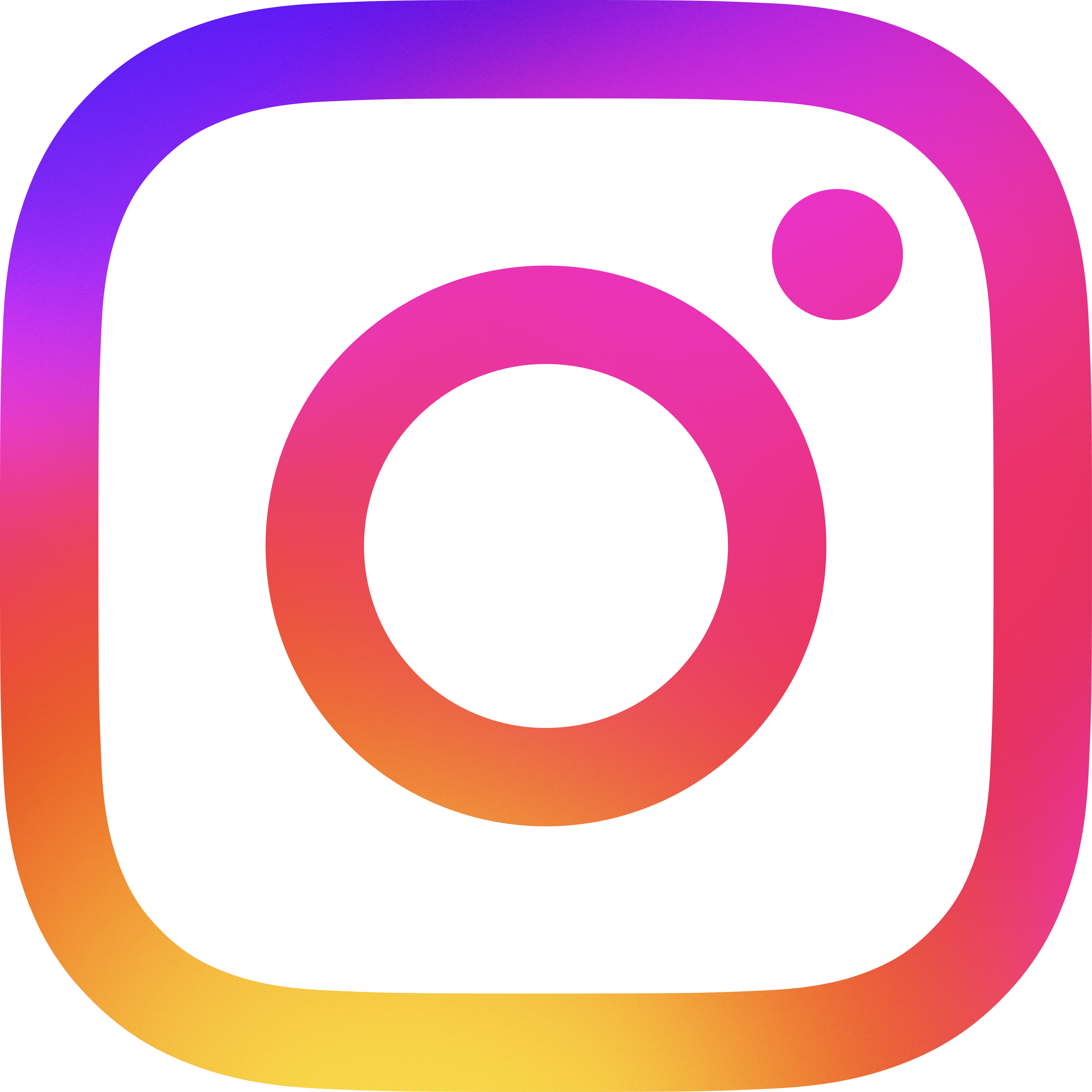「国引き神話」と「大地の成り立ち」のつながり
『出雲国風土記』の冒頭に書かれた「国引き神話」では、八束水臣津野命(やつかみずおみづぬ)という神様が、出雲の国は小さくつくりすぎたといって、4回も土地を引っ張ってきて、出雲の国をつくったとされています。国を引っ張った綱が「薗の長浜」と「弓ヶ浜」で、綱を結んだ杭が「三瓶山」と「大山」でした。
神話の舞台である島根半島は、宍道褶曲帯と呼ばれる大規模な地殻変動が起こったことを示す地質構造で、『出雲国風土記』では引き寄せた陸塊がつなぎ合わさった場所を折絶(おりたえ)と呼び、その場所は地殻変動でできた大規模な断層や褶曲の起こった場所、岩石の種類が異なった地層の境界部分に相当しています。また、『出雲国風土記』で神様が陸塊を綱で引く様子は、約2000万年前から約1000万年前に、大陸が分裂して日本列島が分離し、日本海に島根半島が出現した地球科学のプレート運動にイメージ的に似ています。